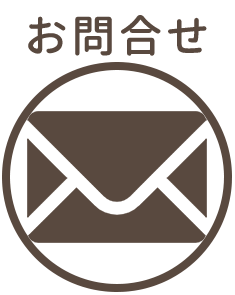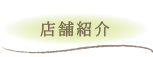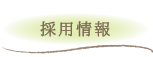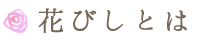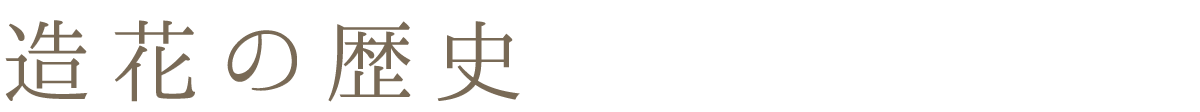

造花の変遷
紀元前の古代エジプトで、エジプト人たちは自然の花で花冠を作りませんでした。
先史の中国では、皇帝の前に出る際、雲母(うんも:鉱石の一種)の欠片で作った桃の花を飾りました。皇帝の寵を得られるのは、もっとも美しい花をつけた者だったのです。
古代ローマでは皮に金銀を塗って造花を作り、戦争で功績をたてた勇者に、花の冠コローナを頭にかぶせて武勲をたたえ祝福しました。その宴席では、造花が豪華な雰囲気を作るために欠かせない存在でした。
中世の後半に、イタリアからフランスへ造花を使う風習が伝わり、花で飾った帽子を作る手工業はフランスの独占的な職業になりました。貴族たちは社交界で、優雅な色彩、豊富な色調を競い合いました。造花は手工業であると同時に、ひとつの芸術でもあったのです。このころの造花は空想の花が多く、写実的な、つまり実在する造花を作り始めたのは1700年頃と言われています。そのころになると、布製の豪華な造花が一般庶民の間でも広く用いられるようになります。
手工業で作られていた造花業に革命が起きたのは、1770年代のこと。スイスで打ち抜きの技術が開発され、一度に何枚も花弁や葉を切ることが可能になりました。次いで、葉脈や花の形を型押しすることが考えられました。これらの技術が今日の造花に大きな影響を与えたのは言うまでもありません。フランスを中心に「絹の花」の需要が高まります。その後、アメリカにも造花は伝わっていきました。アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンの就任式には、この絹の花がたくさん使われたと言われています。
1956年イタリアのボスコー社が、プラスチックを材料としたプラスチック造花を開発します。アメリカの造花会社と提携し、全米に販売し始めました。生産は賃金の安い香港に集中するようになり、世界に広がっていきます。
日本にこの香港製の造花が入ってきたのは、1962年のことです。大西造花がいち早く製造を開始し、「ホンコンフラワー」の名で販売されました。「世紀の造花」というキャッチフレーズで広がったこの造花は、当時の日本の主流だった紙製の造花とは違い、水洗いができ、変色せず、安く大量生産ができるということで流行しました。
その後、改良に改良を重ねられ、技術も大幅に向上し、かなり精巧に生花を模造することが可能になりました。その進化は現在でも続いており、年々、生花と見分けがつかない品質の造花が誕生しています。

日本の文化の中で
ですが、これ以前に日本に造花の技術がなかったというわけではありません。
奈良時代、祝宴を催したときに、草や木の花の造花を、雪で作った岩に配したという事例があります。人々の魂振り(たまふり:活力を失った魂を再生すること)や、鎮魂(ちんこん:魂を落ち着かせ鎮めること)の意があったとされています。
平安朝時代には、挿頭花(かざしばな)という、紙の造花を頭に飾る風習がありました。贈り物などに添える金銀糸や色糸で作った松や梅、挿頭(かざし)としてつける金銀の造花のことを「心葉(こころば)」呼び、「紫式部日記」などにその記述が残されています。また「花の木にあらざらめども咲にけり」という歌があります。これは古今集の中の一首ですが、「削り花」という丸木を薄く削って花の形にした造花のことを指しています。
室町時代には「有職造花(ゆうそくぞうか)」という、京都御所を中心に発達した絹の造花が誕生しました。もともと公家への献上品を始まりとする文化ですので、現在ではひな人形の桜橘にその名残が見られるほどとなっていますが、今もなお、脈々と続く日本の文化のひとつです。
江戸時代には「お細工物(さいくもの)」と呼ばれる、ちりめんなどで作られる造花が見られました。仏壇用造花やそれを作る専門の造花師、宮中の御用造花師なども登場します。また「花かんざし」(造花で飾ったかんざし)は江戸の名物にもなりました。
今日みられるような造花は、明治以降にヨーロッパ風の婦人洋装が流行するようになってから登場します。女性の職業教育機関では、刺繍、編物などの家政科のひとつに造花がありました。ファッション用として需要のあった造花は、皇室にも納品されていました。
ほかにも、1000年以上続く東大寺のお水取りでは、紙で作った椿の造花が欠かせません。薬師寺の修二会(しゅにえ)は「花会式(はなえしき)」とも呼ばれ、十種の造花がご本尊に供えられます。寺社のなかには、衛生の問題から供花に造花を推奨しているところもあります。デパートやホテルのロビーの装飾、テレビ番組の舞台背景、お店の中の飾りつけ、ご自宅のお手洗いや玄関、女性を中心としたファッションの一部。
現在でも、私たちの生活と文化には、造花が色濃く存在しているのです。

ひとと造花
思えば、私たちはしばしば贈り物に花を使います。誕生日や記念日に花束を贈る方は少なくありませんし、卒業式や入学式などの式典で胸に飾るコサージュも花であることが多いです。結婚式で花嫁が持つブーケの由来は、花婿がプロポーズの際に手渡した花束だとされています。
ひとは生者だけでなく、死者にも花を贈ります。約3万年前に絶滅したネアンデルタール人には、死者を埋葬し、死を悼んで花を供える習慣があったという説があります。これには否定的な意見もありますが、少なくとも、現在の私たちは死者を悼むときに花を手向けます。お葬式では棺を花で埋め、お墓には花を供えます。
奈良時代の日本に住む人々が、魂振りと鎮魂に花を使ったように、ひとが生活をしていくためには、花が必要だったのかもしれません。
では、どうしてひとは造花を求めたのでしょう。
花の命は短い。それはこの地球が始まったときから変わらないことです。
その美しさをできるだけ長くこの手に残したい。長持ちする花がほしい。
ひとが花を求めるとき、そう考えるのはある種当然だったのかもしれません。
かつて私たちの祖先は、アフリカ大陸から歩きだし、海を越え、山を越え、はるか遠く離れたこの日本にまでたどり着きました。造花もまた、紀元前2700年のエーゲ海からはじまり、長い年月をかけてこの国にまで伝わりました。それは決して安寧な道のりではなかったでしょう。ひとの歴史がそうであったように、造花もまた衰退と繁栄をくり返してきました。そしてそれは今後も続いていくでしょう。それがまた困難の道であることは、想像に難くありません。しかし、造花の祖が魂振りと鎮魂であるかぎり、わずかながらでも道は進んでいくのだと確信しています。
造花はようやく今、一つの事業として花開こうとしています。
この試みが、紀元前から続く造花の歴史の中のひとつの礎となるように、私たちは日々努力を続けていかなければと思うのです。

花びしが造花製造業をしていた頃、苦楽を共にした道具たちです。

染まり具合を見るサンプルと一緒に染料の配合や割合など細くメモされています。